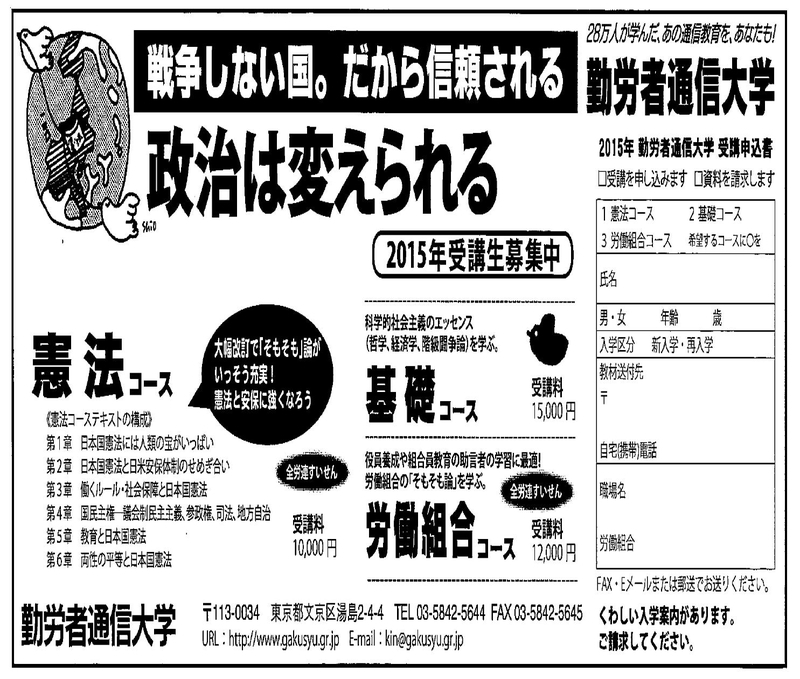憲法コース受講生からだされた質問と、それへの回答を掲載します。
**********
質問:「憲法は応能負担原則という考え方をとっている」と書かれていますが、第84条、第29条に直接、応能負担のことが書かれているわけではないので、わかりにくいのですが。
ご指摘のとおり、たしかに憲法には応能負担原則のことは直接的には言及されていません。
しかし、憲法全体をよく読めば、税負担の公平を実現するためには、「応能負担の原則こそ憲法原理に適した制度」(176ページ)なのです。
テキストで言及した第84条、第29条はもちろんのこと、補足すれば、第14条にある「法の下の平等」が大切です。
この平等原則を形式的にだけでなく実質的に保障することが重要です。
これを税制に応用すれば、租税法律主義(第84条)とともに「公共の福祉」にもとづく財産権の制限(第29条)についても考慮しなければなりませんから、応能負担ということになるのです。
しかし、憲法全体をよく読めば、税負担の公平を実現するためには、「応能負担の原則こそ憲法原理に適した制度」(176ページ)なのです。
テキストで言及した第84条、第29条はもちろんのこと、補足すれば、第14条にある「法の下の平等」が大切です。
この平等原則を形式的にだけでなく実質的に保障することが重要です。
これを税制に応用すれば、租税法律主義(第84条)とともに「公共の福祉」にもとづく財産権の制限(第29条)についても考慮しなければなりませんから、応能負担ということになるのです。
たとえば消費税です。
「みんなが同じ額を負担するから平等だ」という人もいますが、収入が低い人ほど負担が高くなるという逆進性が創設時から問題になっています。
そもそも消費税は、輸出戻し税(179ページ注)などにもみられるように、その実態は税金ではなく、“やらずぶったくりの大企業奉仕の収奪金”というべきです*。
消費税の税収はいまや国費の20~30%を占めており、所得税や法人税よりも多くなってきています。
また、所得税でも応能負担にもとづいた累進制が緩められたり、法人税率が下げられたりするという不公平がまかりとおっていることも問題です。
一刻もはやく消費税依存から脱却し、所得税や法人税などの直接税を中心の税制にしなければ、貧困と格差はますますひろがってしまいます。
民主的税制の基本(175ページ注)をおさえながら、制度全体に応能負担原則を貫いていくことが、いまほど重要なときはありません。
そのためにも、税負担の公平は憲法の平等原則にもとづいたものであり、その実現は応能負担によるべきだということを、きちんとおさえておくことが大切です。
なお、後者のページには参考文献もいくつか掲載していますので、参照してください。
**********